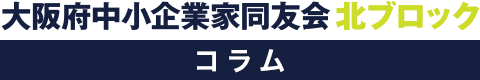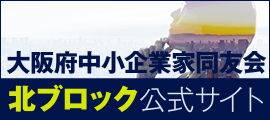『求人募集・採用について 第1部』 (全3部)

新年度がはじまり労働市場の動きが活発になる時期になりました。
一般的に人手不足であるとは言われますが,実際には人材が適切に募集できている会社とそうでない会社があります。
なぜそのような違いがあるかを考えて見ると,求人の条件以上に求人の進め方に不十分な点がありそれを見落としている場合のほうが多いようです。
ご存じの通り求人~採用の流れとしては以下の通りですが,この流れのうちのどれかの部分が不十分であればその部分がボトルネックとなり採用全体が計画通りに進みません。
ここでは,ある程度事業計画や理念・ビジョンが整っていると言う前提で,募集~採用に関してあらためて注意しておく事柄をまとめます。
1.自社の業務の棚卸し→2.不足している人材の要件・要員数の確認→3.採用計画の作成→4.求人募集→5.採用選考→6.採用→7.定着・研修教育・訓練
募集がうまくいかない理由は労働条件にあらず
1. 自社(事業部門)の業務の棚卸し
慢性的に人材不足のためにどんな業務でもよいから今すぐに人材がほしい,という会社・事業所であってもその会社・事業所の全ての業務に対して人材が不足していると言うことはまれです。
営業・企画分門,開発・製造部門,バックオフィスなどの部門,部署,業務のそれぞれについて
・業務の種類
・業務の専門性
・業務に必要な時間
・その業務進まないとした場合の損失
などを列挙します。業務に必要な時間の総合計は従業員の延べ労働時間とほぼ一致するように具体的に調べます。
同時に,各業務の重要性と優先順位をつけて
業務ごとに100%(1.0倍)~10%(0.1倍)などの乗率を決めます。
必ず遂行しなければ会社の動きが止まる・売上に直接響くものは100%として
優先度の高い・低いを数値化しておきます。
2 不足している人材の要件・要員数の確認
現在の人員に対して何%程度の延べ労働時間の増加とどの程度の専門性の向上があれば,
・不足している人材・労働力がカバーできるのか,
・現在見えない損失となっている業務の遂行と業績の拡大が図れるのか
を確認します。延べ労働時間については短時間の残業でカバーできている業務も含めてリストアップします。
このときに,会社・事業所の考えられる全ての業務についての合計の延べ不足人員数を求めるのではなく,上記1.で決めた乗率を考慮します。会社・事業所にとって優先すべき業務について加重平均した形の不足人員数で考えていきます。
※人件費率は会社・業種ごとにある程度決まってしまうので,人件費率がその枠に収まらない場合には業務ごとの生産性や業務の優先順位に改善・修正すべき箇所があるはずです。そうでなければそもそもの事業計画の売上見込が不足していることになり事業計画自体修正が必要と考えられます。
同時に現在の従業員ごとのの業務の偏りもわかってきますのでそれを修正していきます。
業務量の偏りを改善したり社内連絡の仕組みを改善するだけで人手不足感が大きく減る会社・事業所も存在します。
3 事業計画にあった採用計画の作成
1) そもそも募集が必要か。
まず考えておきたいのは
①3年後と10年後に現在の従業員の状況はどうなっていそうか。
確実に一定数出てくるものに定年退職者,介護離職者,結婚出産育児離職者,それ以外にも突発的にいろいろな離職者は発生します。それらをあらかじめ業界業種ごとの離職率で確率的に推計しておきます。
②3年後と10年後に必要な人材の把握
現在の不足人員数だけでなく,事業計画にもとづいて事業ごとに拡大縮小を考慮します。特に事業所・営業所・店舗等を増加させる場合は重要です。
すると,
・各従業員雇用区分ごとに何人必要か。
・どんな方法・手法で求人するか。
・それらの人員の属性は新卒や第二新卒などの若年層で求人するか,ベテランを含む中途採用で求人するか。
などがほぼ自動的に決まってきます。
2) どんな人を採用するか
上記1)で述べた形で,専門職,通常職,若年層,中高年層,フルタイム・パートタイム・短時間,無期雇用か有期雇用か・・・に当てはめていきます。但し一般的には,
能力・技術・技能的な基準,年齢・性別・その他個人にもとづく属性的な基準
よりも
コミュ力的な基準
のほうが重要です。
※中小企業では,ひとりの従業員に多様な業務を任せることが多くなります。業務内容の細分化が難しく多くの従業員,部署との調整や連絡が発生しやすいのである程度コミュ力があったほうがよいと言えます。
更に,
・何人採用するか。
・いつまでに採用するか。
上記1)の①,②から決まります。そうでなくとも災害や家庭の事情により突発的に離職する場合など,人が足りなくなる場合はあるので,数年以内に起こりうる可能性のある離職・休職は先に考慮しておきます。
3) 採用計画における新卒と中途採用のメリットデメリット
いわゆるコロナ後になって若年層の就職観が大きく変化してきました。長く一つの会社で働くことをはじめから希望しない求職者が増えてきました。このような労働市場環境になると,専門知識が少なく教育研修の時間的労力的経済的コストが大きい若年層を雇用することに対するメリットが小さくなってきています。
ここで気をつけたいことは,だから若年層の採用が損で中高年層の採用が得,であるとかその逆であると言うようなものではありません。年齢に限らず個々の求職者応募者の予想される能力を精査して会社にとって本当に有益な人材かどうかを判断するべきということです。社会全体として職務等級やジョブ型をはじめとした同一労働同一賃金にもとづいた
給与体系と採用が求められていくということです。
※職務等級やジョブ型などの制度は会社内の業務を精緻に棚卸をしておかないと運用できません。
 著者
著者
田村博社会保険労務士事務所
代表社員 田村 博(社会保険労務士)
豊能支部
info@simple-jinji.com