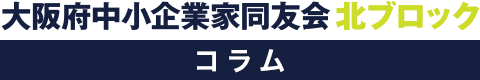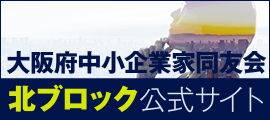『求人募集・採用について 第2部』 (全3部)

昨今の求人募集の傾向とテクニック
4.求人募集について
母集団と言えるほど求職者応募者を集めることはなかなか難しいことではありますが,母集団が大きくなるほど会社の求める人材に出あう可能性が増え採用成功,定着の確率が高くなります。その状態をめざして,自社homepageやsns,外部の求人媒体やイベント,インターンシップなどを活用し,自社に興味を持つ求職者との出会いを増やすことになります。
母集団が増えると,選考時の従業員の適正だけでなく
・歩留まり予測からその後も計画的な採用が可能。
・従業員の離職率が低下するので事業計画に沿った従業員の研修,教育訓練がしやくなります。
1) 母集団形成のためのメディアの選択
一般的には
・求人広告
・企業homepage,会社案内(web版,紙版)
・一般求人サイト,業界専門の求人サイト
です。
・商工会議所,行政機関,専門学校や高校大学との連携,職場実地体験やインターンシップの活用については,学生に業界・業務内容・企業を知ってもらうよい機会になりますが,通常直接採用につながるものではありません。高校については一部地域・学校種別で実施されているようです。
昨今は,合説,ダイレクト・リクルーティング,アルムナイ,リファーラル・・・
などいろいろと言われていますが,高い費用をかけて職業紹介業者に依頼しても必ずしも成功するとは限りません。
中小企業では社内ではたらく社員全員がリクルーターと考えましょう。従業員のご家族も重要な広報となります。
その他最近では,AIやデータ分析を用いて,応募者の適性や能力を効率的に評価するサービスも増えています。募集ではなく採用選考に関わる部分ですがのちのち定着につながります。
2) 選択のための一般的な考え方
求職者を紹介してくれる業者を利用して比較的効果が高いのは,募集対象が管理職以上である場合や高度専門職や資格職の求職者を紹介してもらうときです。
しかしこの場合でも専門的な職業能力を持った人材はどの業界でも取り合いになっていますので必ずしも見つかるとは限りませんし,すぐに見つかるかというとかなり難しいといえます。
① 費用対効果を考えてどうしてもこの能力技能等がある人材が喫緊で必要だ,という場合にはそれなりの費用がかかってもその専門知識のある求職者を多く登録している(と予想される)紹介会社などに依頼することになります。高い費用をもらうことになる人材紹介会社はその分力を入れて(お金をかけて)探してくれることになります
② それほど差し迫って専門人材が必要ではないが事業計画から考えて必ず必要になりそう,あるいは現在の役職者や専門職者が定年等で退職が見込まれている場合などでも人材紹介会社が有効と考えます。ただ差し迫ってというわけではないので成功報酬型の人材紹介会社が使いやすいところです。
最近は①に相当する人材を紹介する場合にも成功報酬型の人材紹介会社が増えてきましたのでこのあたりは人材紹介会社を上手に選択したいところです。
③ さらに差し迫ってはいないが将来的に専門人材が必要になるだろうとか,現在の従業員で業務はカバーできているがあらかじめ将来的な事業の拡大や変更などを見込んで人材を探しておこうという場合には,産業センターのプロ人材紹介などが有用です。公的な人材紹介ですから普段から多くの登録者がいるわけではないのですが,ぽつんぽつんと良い人材の登録がはいるようで急ぎでなければ役に立ったという会社様に結構出会いました。しかも公的なサービスですから費用がかかりません。このあたりも上手に利用しておきたいところです。
逆に専門性が低くてもよい場合には,
① 会社ホームページに求人サイトを作成する,
② snsで発信すると同時に会社ホームページの求人サイトにリンクをはる,
③ ハロワやindeedなどの求人票をかけるだけ書きこんで会社ホームページに求職者・応募者を呼び込むようにする。
の基本でも十分に成果を上げています。求人メディア作成のときに業者に依頼する場合でも上記1.~3.を丁寧に相談して求人内容に反映させたいものです。
3) 自社求人ホームページとsns
昨今の求人で大きな影響をもつのは
・会社ホームページの「求人サイト」がどのくらい充実しているか
・snsの選び方
・upしているコンテンツとのリンク
です。
snsでは動画が流行っていますが,動画でなくとも静止画を数枚程度ずつ紙芝居パラパラ漫画状態で業務の様子や従業員の雰囲気をupしていくだけで反応は変わります。静止がであれば作成もかなり容易になります。
内容は
(1) 会社の雰囲気が伝わること,
(2) 会社とその周りにうつっている様子がそれなりにきれいであること,
(3) 社員の表情がよいこと,
(4) 社員が明るい雰囲気で作業していること
(5) その上で会社の製造物や商品がわかり業務の内容に何となくでも予想できること
が必要です。
もちろんsnsにupできる情報量は限られますのでこれらの情報を全て表現することは大変であり慣れが必要になりますから自社ホームページに情報を詳細にupしてそのうちの一部をsnsとリンクさせることでsnsから求職者を自社ホームページに誘導していきます。
さらに,本当にエントリーしようと考えている真面目に前向きに考えてくれている求職者や若年労働者の保護者であれば自社ホームページは必ず詳細に目を通します。働きやすそうな会社か,賃金休日などは十分に確保されているかなどが判断されます。
と,ここまで記述するとお分かりだとおもいますが,この時点で自社が求職者から探されて選ばれているかが決まっています。求人に対して応募がほとんどないという会社様はほとんどここまでの対応のうちのいずれかの対応や情報が不足しておりその時点で求職者に選ばれていないといえます。
※働き方改革推進支援助成金や豊中市人材確保促進補助金など採用ホームページ作成に対して一部助成制度があります。
(参考)各SNSプラットフォームのメリットとデメリットを募集に活用する観点からまとめます。
① Twitter
メリット:ハッシュタグの活用で特定のトピックやイベントに関連する投稿を効果的に拡散しやすい。若年層の利用が多い。
デメリット:テキスト中心でビジュアルコンテンツの効果が限られる。
② Instagram
メリット:写真や動画を使いやすく若年層の利用が多い。
デメリット:コンスタントな更新が求められます。運営コストや時間がかかることがある。
③ Facebook
メリット:地域コミュニティにアプローチしやすく企業文化を伝えるのに適している。
デメリット:年齢層が高いこととユーザーのデータプライバシーに注意が必要。
④ LinkedIn
メリット:キャリア志向の高い若者に向きで企業の専門性や働きやすさをアピールしやすい。
デメリット:他のSNSに比べて利用者のアクティビティが低い。
⑤ TikTok
メリット:若年層にダイレクトにアプローチできる。音楽やダンスなど動きのある動画で拡散できる。
デメリット:動画の投稿が一過性であり,長期的なブランディングや情報発信には向かない。
4) 求人票の文言
① ハローワーク求人票でも自社ホームページのURL/addressを記載できる欄があります。
ここは会社概要のページではなく,自社採用ホームページにしておきましょう。
そのページのトップに会社理念と上記の画像や動画(リンク先でも可)をのせ,会社として理念に沿った社会貢献的活動に十分に配慮した状態で,しかも現在勤めている従業員がこんな良い表情で業務に打ち込んでくれている,とアピールすることになります。
② 見てもらえる求人票
※ アピールすべき事柄は紙媒体でもサイトでも同じです。労働条件等は全て記載しなければなりませんが,求職者に最初にヒットする部分は見出しと会社の雰囲気です。
1.見出し
・短くて分かりやすいタイトル
・求職者の興味を引くフレーズ
を求人ターゲットによって使い分ける必要があります。
若年層であればほとんど働いた経験がないために「夢」「挑戦」などの語がヒットしやすのですが,
中途採用,特に専門職中高年の層にとっては「夢」などよりも仕事の成果と報酬の両方で「自分を認めてほしい」「認めてくれる」事の方が重要です。(能力に応じて)責任や裁量が十分に与えられる,こと,十分なリターン(金銭的なものだけなく,気持ちの部分が大きい)が伝わるようなコピーが大切です。
(例)若年層向け
「フレンドリーなチームで、楽しく働きませんか?」
「一緒に成長しよう!未来を創るメンバー募集!」
「地域密着の温かい職場で、一緒に働きましょう!」
「職業訓練でスキルアップ!安心して働ける職場へ」
転職者向け
「あなたの経験と知識が必要です。共に未来を築きましょう!」
「あなたの個性を活かせる職場がここにある!」
「働きやすさとやりがい、どちらも手に入れよう!」
「柔軟でクリエイティブな働き方!」
2. キャリアパス
やる気のある若年層について特に重要です。特に近年の若年層の方は,スキル,技能,資格を得るための学習機会などは自ら探すものではなく他者や会社などから与えられるものと認識している方が多くなっている印象です。
※人材開発支援助成金や大阪府スキルアップ支援金など従業員のキャリアアップに利用できる助成金が設定されています。
3. 呼びかけ と 現社員の声
・求職者に対するメッセージを添える
・自分たちのチームの一員になることの魅力を強調
・実際に働いている社員の体験談のインタビューやコメント
・社員の成功体験や日常のエピソード
理念のところで社長の想い,呼びかけのところで社員の気持ちを記載しておきます。
若年層の採用であれば同年代の方の意見・感想が重要です。並行してキャリアパスが見えるように一回り上の年代の方で上手に昇進昇給や育休からの復帰などの経験のある方の意見・感想を記載しておくと効果的です。
5) エントリーしてもらうために
・エントリーシートのオンライン化/スマホ対応は必須です。
求職者のほとんどはスマホで仕事を探しています。スマホ操作だけでエントリーが完結するようにオンラインフォームで簡単に応募できるようにしておきます。これによって応募のハードルを下げることができます。
 著者
著者
田村博社会保険労務士事務所
代表社員 田村 博(社会保険労務士)
豊能支部
info@simple-jinji.com